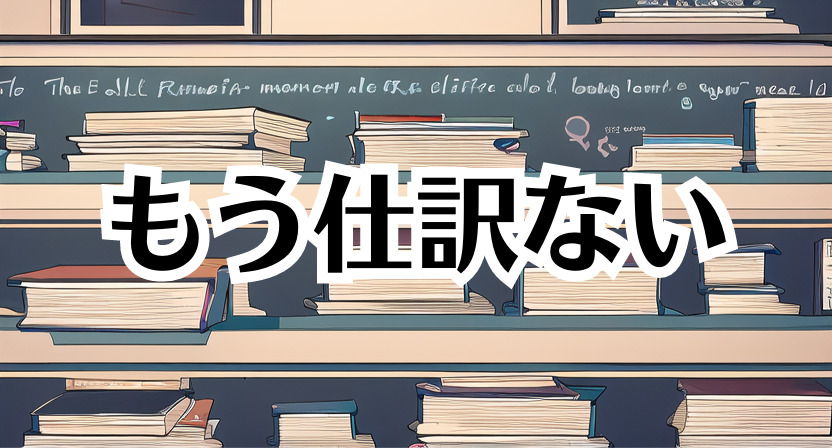目次
退職給付引当資産(退職給付引当金)を一つのサービス区分に計上する
全社協や県社協の退職共済に入っているとき、退職給付引当資産(退職給付引当金)を計上しているはずです。
法人内で拠点やサービス区分が一つである場合は関係ありませんが、2つ以上のサービス区分で退職共済に加入している職員がある場合、掛金の支払いや異動など、煩雑な会計処理が存在します。
「いっそ、退職給付引当資産(退職給付引当金)を一つのサービス区分にまとめてしまえば、楽なのでは?」と思うかもしれません。
ここでは、退職給付引当資産(退職給付引当金)を一つのサービス区分に計上するメリットとデメリットを挙げてみたいと思います。
メリット
各サービス区分への配賦処理や期末の異動処理がなくなり、事務負担が減る。
デメリット
人件費の不正確さ
退職給付費用は、職員を雇用することに対して発生する費用です。
給与等と同じ基準で計上すべきものです。
それを支払うタイミングが給与や賞与とは異なるだけであって、給与「のようなもの」という性格に変わりはありません。
退職給付費用(退職給付支出)だけが他の人件費科目と異なる基準により計上されることになれば、各サービス区分の人件費や収支額が会計上正しい数値にはなりません。
また、退職があった際にも、退職者の出たサービス区分と経理処理を行うサービス区分が異なります。
退職金の支払い時にも、サービス区分ごとの人件費が正しく見られなくなります。
指導監査での指摘事項
社会福祉法人会計基準が求めている処理ではないため、指導監査等で指摘を受ける可能性があります。
まとめ
退職給付引当資産(退職給付引当金)を一つのサービス区分に計上すると、事務負担は軽減されますが、損益の数値が実態とかけ離れたものとなってしまいます。
また、指摘を受ける不安もあります。
社会福祉法人会計基準が求めているように、退職給付引当資産(退職給付引当金)は、退職共済加入者の所属するサービス区分で処理する方法をおすすめします。